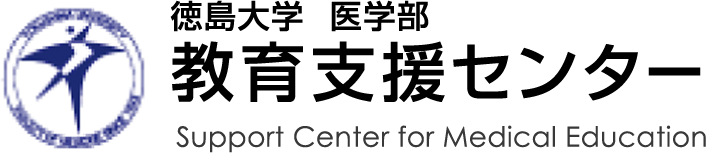平成28年度PBLチュートリアル講習会
- 日時:平成28年7月13日(水)18:00-20:35
- 場所:スキルスラボ8(総合研究棟2階)
- タスクフォース:赤池雅史1,2、三笠洋明1、吾妻雅彦2、岩田 貴2,3
1医学部教育支援センター、2 大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター、
3教養教育院医療基盤教育分野
- 共催:医学部教育支援センター、医学部FD委員会、医学部教務委員会、
- 協力:大学院医歯薬学研究部医療教育開発センター
合計17名の参加があり、ミニレクチャーとシナリオ作成のワークを行いました。参加者によるポストアンケートでは、5点満点で、ミニレクチャーは4.41、ワークショップは4.47、全体としては4.71、タスクフォースの働きには4.59と、いずれも昨年度を上まわる高い評価をいただきました。
■ミニレクチャー「PBLチュートリアル教育が目指すもの」
講師:赤池 雅史
必要な知識・技能の爆発的増加、AIに代表されるテクノロジーの発達、求められる卒業時レベルの上昇がある一方で、高度・安心・安全ならびに専門的かつ全人的な医療の提供、ローカルかつグローバルな視点、予測不能な未来を切り開く力が強く求められており、自立・協働・創造の力を持った人材育成が必要である。このような人材は専門性と汎用性の両方の能力を兼ね備えることで、単に専門的知識を修得することに留まらず、それを実践で活用できる能力、すなわちDoesのレベルの能力を有することが必要である。このような視点から、近年、アクティブ・ラーニングが非常に重視されており、学習者がそれを進めるためには、学修意欲、文章力、プレゼンテーション力、協働力、省察力が必要と考えられている。また、日本の医学生は米国の医学生と比べて、卒業時点でhistory taking、physical examination、clinical reasoning、case presentationの能力が劣っていると指摘されており、これらの能力をDoesのレベルにまで引き上げるために、準備教育を含めた臨床医学教育の充実が必要である。
PBLチュートリアル教育は、シナリオ(ペーパー症例)、小グループによる自己決定型学習、チューターによるファシリテーションの3つの要素で構成されており、診療の流れをシミュレーションしながら、ブレインストーミングの手法でディスカッションを行い、事実の把握、仮設の立脚、知るべきことの抽出、学習課題の作成、自己学修、学習成果発表の過程を通して、4つの学習項目(基礎的、臨床的、社会疫学的、行動科学的)について学んでいく。さらに学生はこの学修プロセスそのものについても常に振り返りを行うことで、アクティブラーナーへの成長を目指す。チューター教員は、このような自己決定型学修プロセスをファシリテートすることが役割である。そのためには、アクティブ・ラーニングの観点から、チューターは一方的に知識を伝授せず、学生に気づきを促すことが必要であり、雰囲気作り、傾聴、見守り、学生への問いかけ、学修方法のアドバイス、自分の経験の紹介が重要である。
■WS「効果的なPBLチュートリアルシナリオ作成」
PBLチュートリアルでは、アクティブ・ラーニングの原則に基づいて、単なるに知識の丸覚えにならないように、ブレインストーミングを基本として、振り返り(省察)を繰り返しながら、思考力、協働力、プレゼン力を修得していくようにデザインする必要性があり、それにはファシリテーターとしてのチューターの役割と自己決定型学習を促す優れたシナリオの作成が重要である。
そこで、1)学習内容の量と質が、4年次4~12月の学習段階に適している、2)基礎医学、臨床医学、社会疫学、行動科学の学習項目をすべて含む、3)臨床の文脈の中で学生自身が考えることが可能、4)学生のグループ討論が活発になる、5)学生の自己決定型学習が促進される、6)チューターによるファシリテートがやりやすい、の6つの条件を満たすシナリオ案の作成を参加者全員が行った。全体発表では、パーキンソン病、小児気管支喘息、多発性骨髄腫のシナリオが取り上げられ、学習のアウトカム、学習課題、ストーリー(症例、場面、展開)、呈示データ、議論を促進するチューターの質問、必要な物品・設備の各項目について、意見交換を行った。患者映像や動画を活用すること、医療制度や患者の気持ちについて学習できるストーリー展開にすること、学生はガイドラインやインターネット情報の中から「正解」を探そうとする傾向があるので、病態・機序と関連づけてディスカッションするようにファシリテートすること等の重要性が指摘された。