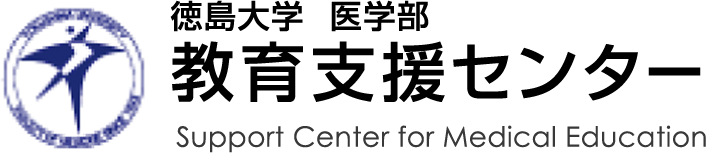- 平成21年1月21日(水曜)17:30 ~ 21:30.MINCSカンファレンス室
- タクスフォース:赤池雅史、三笠洋明、福井義浩(医学部教育支援センター)
臨床講義を担当する臨床系分野から13名の参加があり、梶 龍兒教授(臨床神経科学分野)のご講演と2つのワークショップを行いました。参加者によるポストアンケートでは、全ての内容に対して平均で4点以上(5点満点)のご評価をいただきました。
■イントロダクション「徳島大学の医学教育の現状」赤池雅史(医学部教育支援センター)
平成20年度からの医学科新カリキュラムの概要や臨床講義授業アンケート結果などの説明が行われた。参加者からは、それぞれのプログラムがカリキュラム上で一貫性を持つこと、その目的・役割を明確にし、それを周知することの重要性が指摘された。
■ワークショップ1:「臨床講義の目標・アウトカム」
KJ法を用いて討議し、実体験型の講義を行うとの観点から、臨床講義の目標・アウトカムとして下記項目が挙げられた。
- 臨床医学への興味付け・モチベーション
- 臨床推論能力,診断・臨床決断能力
- カルテ記載
- プレゼンテーション能力
- コミュニケーション能力(学生同士,担当医師との)
- 医学英語の活用
■レクチャー:「神経内科における臨床講義の取り組み」 臨床神経科学分野 梶 龍兒 教授
■ワークショップ2「優れた臨床講義の具体的方法」
KJ法を用いて臨床講義のあり方について討議し、下記の具体的方法が提案された。
- 比較的頻度の高い疾患を対象にする
- 事前に情報を提供し、準備期間を十分にとり、学生に予習をさせる
- 学生に事前に診察させ、それをビデオ上映する
- 学生と事前に打ち合わせを行い、質問を提示しておく
- 講義中および終了後にフィードバックを行う
- 患者参加型の講義(患者さんに講義に出ていただく)
- PBLチュートリアルがサイエンスの学習に偏りがちになることに対して、臨床講義ではアートの学習にも比重を置く
- 一方的なレクチャーではなく、学生との双方向性講義を行う
例:Team-based learningを取り入れる(聴講学生を小グループにわけて討論させる)
例:学生全員参加型で行う(プレゼンテーションを行わせる。カンファレンス形式で聴講学生に質問する。)
- Audience response systemの積極的利用