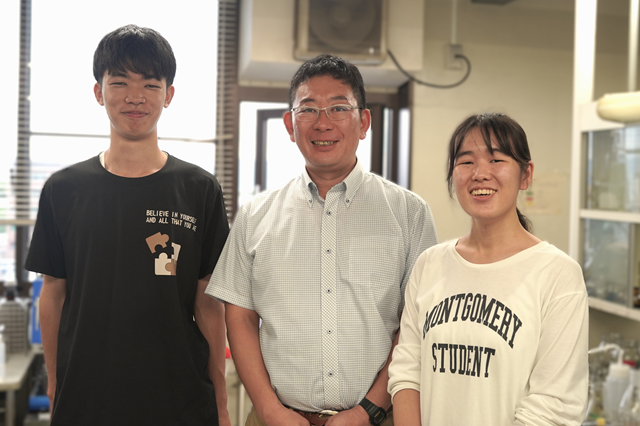【イベントレポート】「SDGs+Beyond」 未来を拓く、プレセッション開催!
9月12日(金) 四国大学交流プラザにて、10月9日(木)に大阪・関西万博で開催されるディープテックイベント「Imagine if...! Deeptech for the Real World」 のプレイベント「ディープテックプレセッション」が行われました。
「Imagine if...! Deeptech for the Real World」 は10月の万博のテーマ「SDGs+Beyond」にちなんで、第1幕「徳島においてSDGsとは」、第2幕「地方都市のディープテック・スタートアップが拓く未来」、第3幕「Imagine if...! 徳島の多元的未来の可能性」の3部構成でSDGsのその先に広がる未来について考えます。
2025年夏号の『とくtalk』でも紹介したように第3幕「Imagine if...! 徳島の多元的未来の可能性」では、社会課題の解決に挑む大学の先進的な技術に焦点をあて、「もし、この研究が世の中にスケールしたらどうなるのか?」について、徳島大学特任助教の石原佑先生をモデレーターに、徳島大学の3名の研究者がトークセッションを行います。
その3名は、海藻の陸上養殖に取り組む岡直宏准教授、AIを活用して心理カウンセラー不足を解消する山本哲也教授、そして青色LEDを使って腫瘍治療に取り組む整形外科医の西庄俊彦准教授です。本学の先進研究が、未来の社会をどう変えていくか、ぜひご注目ください。
このイベントの様子はアスティとくしまで開催される『ビジネスチャレンジメッセTOKUSHIMA2025』で、同時中継される予定です。
徳島にとってSDGsがどういうものなのか。その解像度を高めるために実施されたこのイベントは、SDGsについてのイントロダクション、NPO法人エコロジカル・ファーストエイドの理事長・研究員 佐藤貴志さんによる基調講演、そしてワークショップという構成で行われました。
石原先生は、SDGsが2015年に国連で採択された17の目標で構成されており、2030年をゴールにしていることを説明。「2030年が近づく中で目標達成への批判的な議論もありますが、2030年を超えて真摯に取り組もうとしている事業者も増えており、全体的には良い方向に向かっている」と話し、SDGsとセットでよく耳にするようになった「サステナビリティ」という言葉についても言及。
「世界中の人が今と同じ生活をすると、地球の資源が足りなくなる」と指摘し、「日本人が今と同じ生活を継続するには、地球の資源2.5個分が必要になる。同じく世界全体では1.5個分、アメリカは地球5個分が必要になる」というデータを紹介しました。
「サステナブルは単に現状維持ではなく、抜本的な変化を求めるもの。高度経済成長期と同じ発想で取り組んでも、本質的な変化はなく、ストローを紙に変えるといった小手先の対応にとどまってしまいます。本当に必要なのは、新たな次元から産業を捉え直す発想です。サステナブルという言葉は“持続可能”という表面的な意味ではなく、既存の活動をそのまま続けることが危うい現実を踏まえ、抜本的な変革を求めるもの」と強調。かつては存在しなかったLEDが、今や徳島を代表する技術となったように、現在、大学で行われている数々の研究はディープテック(最先端の科学技術や研究の成果から生まれた、世の中を根本から変える可能性を秘めた技術)の種であると、アインシュタインの言葉を引用しつつ、期待感をもって新しい産業の在り方を模索することの必要性を説きました。
NPO法人エコロジカル・ファーストエイド 佐藤貴志さんによる基調講演
佐藤さんは大学や研究機関に所属せず、個人で研究所を運営する希有な存在です。航空宇宙工学を専門とし、その知識や技術を水質浄化などに応用しています。『NPO法人エコロジカル・ファーストエイド』には、国際NGOなどを通じて世界各地から水質浄化の依頼があり、ほぼ1年中社会貢献活動に専念しているといいます。しかし、環境問題の解決に取り組むため現地を訪れ、そこに暮らす人々に話を聞いてみると、水質浄化を望んでいないケースが多いそう。その理由として、私たち日本人の基準では「きれい」とは言えない水でも、現地の人々にとっては生活に支障をきたすほどではなく、現状で十分だと考えていることが挙げられていました。
こうした水質汚染をはじめとする劣悪な環境の根本原因は「貧困」にあり、今なお人身売買が行われている地域もあるといいます。だからこそ、私たちの価値観や基準だけで判断するのではなく、まずはその地域の生活を理解し、現地の人々の声に耳を傾けながら、共に問題の解決に取り組むことが大切だと語ってくれました。
自身のプロジェクトの本質は「子どもたちの命を守り、自分の夢に向かって歩み出す力を身につけさせること」といい、ネパールで行ったエコツーリズムについても紹介しました。
エコツーリズムとは、環境がテーマの修学旅行のようなもの。エコツーリズムの参加者は、村に対して1人3,000円程度の参加費を支払い、得た利益は村全員で分配します。日本円で50円はネパールの1,000円程度。仮に10人の旅行者を受け入れれば、村全体で3万円の収入を得ることに。3万円は現地では大金。経済的自立支援が可能になるだけでなく、環境面での創意工夫が面白ければツーリスト獲得にも繋がるため、環境問題の解決も叶います。
「例えば環境問題を解決しようと、そればっかり見ていても解決できない。その周りを勉強することが大事。広い視野を持って、問題の本質を捉えることが重要」という佐藤さん。「地域の課題を解決するには時間がかかるけれど、思いやりのある人が増えれば、より良い社会をつくることができる」と、力強く話します。
また、日本人は集団で同じ目標に向かうのが得意な一方で、その流れの中で個性や長所が埋もれてしまうことがあると指摘。「一人ひとりが自分の個性を活かしながら同じ方向を向き、得意なことを持ち寄って協力することが大切。SDGsの中にある『誰1人取り残さない』というキーワードを達成するためには、人と自然に対して、ほんのちょっとの思いやりを持つことが必要。周りの人を笑顔に、あったかい気持ちにできる人が増えれば、あたたかいまちづくりが叶う」というメッセージで締めくくりました。
NPO法人エコロジカル・ファーストエイド
http://eco-1st-aid.com/
※佐藤さんは10月9日(木)に大阪・関西万博で開催されるディープテックイベント「Imagine if...! Deeptech for the Real World」 の第1幕「徳島においてSDGsとは」にも登壇されます。
SDGsの18番目の目標を考えるWS
ワークショップは3つのグループに分かれて、SDGsの18番目の目標となるような、徳島ならではのテーマを考えました。
まずはSDGsの1~17のそれぞれのテーマについて話しあう参加者たち。そのテーマを象徴する事象とそこから受ける印象について書き出しながら、和やかなディスカッションが行われました。
短い時間で様々な意見が発表され、「徳島の豊かな食と阿波おどりで国際交流を活発化し、世界平和を目指す」というものや、高齢化や人口減少など「課題先進県」といわれる徳島だからこそ、その解決のために真っ先に挑める実証実験場となる「徳島国」を作ろうという案など、「誰もが安心して住み続けられる地域であるには」といった課題を共有し、考える時間となりました。
10月9日(木)に大阪・関西万博で開催されるディープテックイベント「Imagine if...! Deeptech for the Real World」 では、さらに活発な議論が展開されることが予想されます。当日は来場者が徳島県のテクノロジーや製品に触れ、未来を体感できるイベントや物販などもあり。ぜひご来場下さい。
「SDGs+Beyond」Tokushima SPACE
日時:令和7年10月8日(水)~10日(金)まで各日10:00~17:00
場所:大阪・関西万博関西パビリオン「多目的エリア」
※9日(木)・10日(金)のステージイベントは、ビジネスチャレンジメッセTOKUSHIMA2025においてライブビューイングを開催。