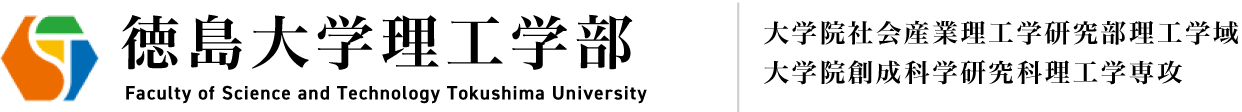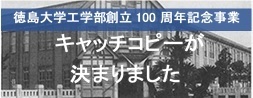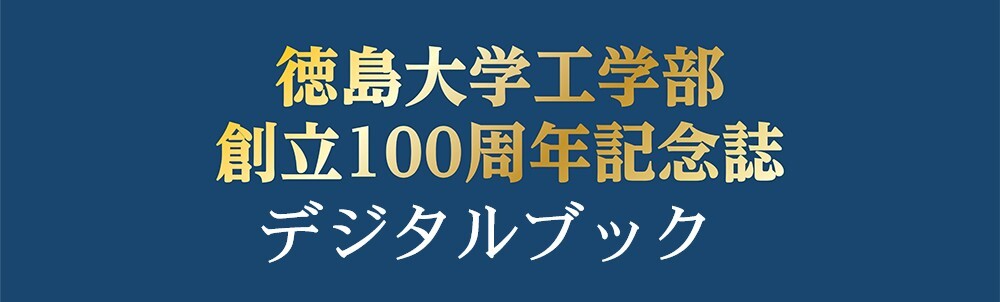コースの詳細
応用化学システムコースでは、新規高機能性材料の設計、合成手法を研究する物質合成化学、物質機能を微視的立場から解析、解明する物質機能化学、および化学工業における製造プロセスの開発と装置設計・保全に関わる化学プロセス工学の3つの分野で教育・研究を行い、現代の化学技術の飛躍的発展の一翼を担う人材の養成をめざします。そのためには基礎学力と柔軟な応用力が必要であると考え、当コースでは自然科学と工学にわたる俯瞰的な知識を系統的に体得するとともに、幅広い教養及び倫理観を身につけ、「ものづくり」に関わる現場で進取の気風をもって柔軟かつ力強く活躍できる人材を輩出することを目標とします。
コースの特徴
応用化学システムコースの教育は、広く理工学基礎科目とコース専門科目に重点をおいており、化学の基礎を習得できます。またコース専門科目では実験を重視し、講義・演習で学習した内容を、実験を通じてさらに理解を深めます。他にも、危険物の取扱いと災害防止、環境問題、工業倫理など広い観点から講義が開講されます。他にも TOEIC-IP の受験により英語能力の把握と向上に役立てます。また少人数によるグループワークでは、学生が自ら設定したテーマに関する調査結果を口頭発表し、能動的学習意欲やプレゼンテーション能力を高めます。さらに新入生研修やスポーツ大会などを通じて、学生と教員の親睦を深めます。
講座の紹介
物質合成化学講座
有機化合物・高分子化合物の合成、分離分析、反応メカニズムの解明などの基礎化学とその手法を応用して、高付加価値物質、高機能性材料の創造について教育・研究します。有機合成化学と高分子化学の研究グループがあり、生活に役立つ新しい物質、素材をつくる夢を追求します。21世紀は真の意味で原子・分子の時代といって過言ではなく、当コースのめざしている「分子設計」の夢は果てしなく広がります。
物質機能化学講座
物質が有する様々な機能の測定、解析、活用に関する教育・研究を行います。我々の周りには天然由来や人為合成の様々な物質があり、新たな機能を意図して新規物質を合成する場合もあります。物質機能の理解を通して、物質を自在に扱い機能を創造していくことが、化学を学ぶ上での真の醍醐味と言えます。
化学プロセス工学講座
高度な現代社会では、「画期的な新機能」と「環境へのいたわり」を同時に満たす材料や反応の創造し、それを実際のプロセスで実現することが求められています。21世紀はまさにこのようなプロセス開発が望まれる時代となり、これらの目的を達成するために日々学生と教員が研究に励んでいます。