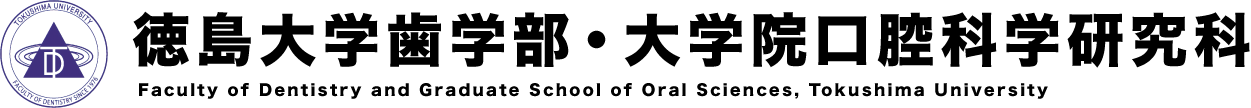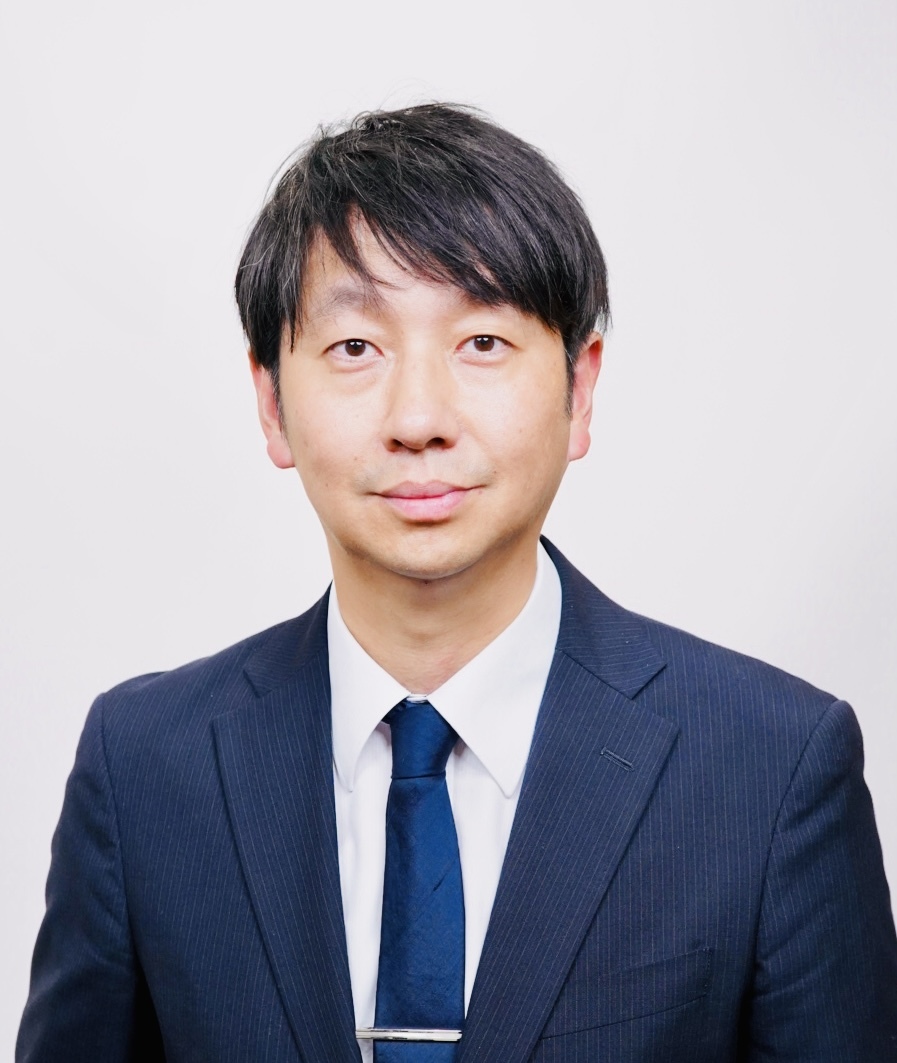松本 真司 教授 メールアドレス smatsumoto@tokushima-u.ac.jp
口腔生理学分野では、3次元培養技術やオルガノイド技術を用いて、以下の主要な研究テーマに取り組んでいます。
1.唾液腺の構造と分泌機能の再現と、調節メカニズムの解明
2.舌の味蕾細胞の機能とその制御メカニズムの研究
3.口腔粘膜上皮のバリア機能の再現と、恒常性維持機構の解明
4.口腔関連上皮幹細胞の特性解明と再生技術の開発
5.口腔疾患を再現するin vitroモデルの構築と病態の解明
6.口腔機能が全身の生理機能と疾患に与える影響の解明
7.核酸医薬による関連疾患に対する治療法の開発
これらの研究テーマを通じて、口腔の健康増進と疾患予防に貢献し、研究成果を社会に還元することを目指しています。また、臨床現場のニーズや課題を的確に捉え、それらを基礎研究にフィードバックすることで、より実践的かつ革新的な研究に取り組んでまいります。
Adobe Reader
閲覧履歴
このページと関連性の高いページ