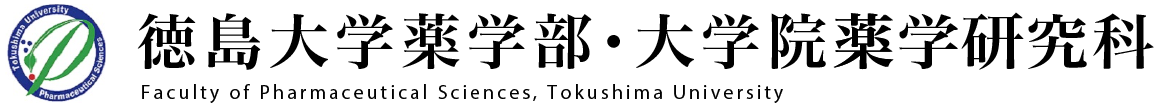薬理活性海洋天然物の構造決定
足摺岬や室戸岬をはじめとする四国沿岸、および沖縄本島、石垣島などに採取旅行を行い海藻、スポンジ、軟体サンゴなどを採取し、それらの化学成分を嘆離・構造決定する。さらに得られた化合物の薬離活性試験を行う。海洋から採取したカビを培養し薬理活性物質を単離する。
NMRスペクトルによる絶対配置決定法の開発
キラルな二級アルコールの絶対配置決定に普遍的に使用されている新Mosher法をさらに発展させ、キラルカルボン酸の絶対配置を決定するためのPGME 法を開発した。最近になってキラルスルホキシドの絶対配置決定法「スルホキシイミン法」やアレンの絶対配置決定法「MPPO法」を開発した。現在さらなる新しい方法論を開発中である。
水圏生物の生理現象に関与する化学物質の研究
これまで海洋生物をはじめとする水圏生物が生産する化合物について、主として構造解析や実利的な薬理活性などが研究されてきたが、水圏生物に含まれる化合物がその生物に対してどのような意味を有するのか解明された例は極めて少ない。その一例が「ミジンコカイロモン」である。淡水の池に普通に生息する単細胞緑藻イカダモにミジンコを飼育した培養水を加えるとイカダモが4~8細胞へ形態変化を起こす。これはイカダモがミジンコに食べられにくくするための防御機構と考えられている。この研究室では長年にわたってミジンコカイロモンの研究を行って来たが、2005年ついにカイロモンが硫酸アルキルエステルであることを突き止めた。

海洋天然物の化学変換
沖縄産の軟体サンゴであるオオウミキノコから極めて大量に得られるセンブレン(ジテルペン)を強い薬理活性を持つ化合物へ化学変換する研究を行っている。
C-Pカップリングの構造決定への利用
NMRスペクトルにおいて、リン原子(P)は隣接する水素や炭素C-13に大きなカップリングを示す。特に炭素とリンのカップリング(C-Pカップリング)に注目し、化合物にリン酸基を入れることによりその化合物の構造を効果的に決定する方法論を開発している。 キーワード:海洋天然物、構造決定、軟体サンゴ、海藻、海洋性カビ、テルペン、カイロモン、アレロパシー、プランクトン、機器分析、NMRスペクトル、絶対配置決定、新Mosher法、PGME法、スルホキシド、キラリティー、アレン、MPPO、光学分割、C-Pカップリング
Adobe Reader
閲覧履歴
このページと関連性の高いページ