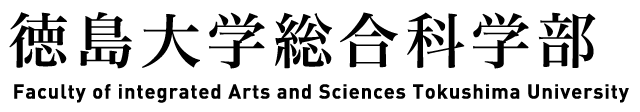サークル活動が卒業生制作のヒントに カラーユニバーサルデザインへの挑戦(2021冬号)
サークル活動が卒業生制作のヒントに カラーユニバーサルデザインへの挑戦(2021冬号)

総合科学部 社会総合科学科 3年
平尾 更紗 (ひらお さらさ)さん
My Life Situation
部活: らぱっと編集部
アルバイト: カフェ勤務
趣味: 散歩
映像・デザイン、美術教育、メディアアートなどを学ぶ佐原先生のゼミに所属する平尾さんが、卒業研究にしようと思っているのが、カラーユニバーサルデザインです。カラーユニバーサルデザインをテーマにしようと思ったきっかけは、サークル活動。学内で配布しているフリーペーパー『らぱっと』の編集部で活動し、「いかに可愛く作るか」と誌面デザインに悪戦苦闘していたときにふと、「誰もが読みやすいデザインとは…」と思い、何気なく風景の一部として捉え、不自由していなかったものが、多くの人にとって見やすいものかと考えるようになったといいます。 「色盲、色弱の人は、日本人男性の5%、女性の0.2%程度で、1クラス(40人程度)に1人はいる割合です。男性の5%という数字は血液型でいうとAB型の男性人数とほぼ同じ割合でいるそうなんですが、認知が広まってないのが課題です。自分が色盲、色弱ということも気付きにくく、『黒だと思って書いていたら赤だった』と周りから指摘されて気付くケースもあるそうです」。卒業制作として、学内の地図やサイン(表示)をカラーユニバーサルデザインに合わせて表示し直したものを作ろうと、論文を読んだりしながら知識を深めています。そうしたデザイン活動は悪い部分を発見・分析して処方箋を提案する医療のような活動だといいます。
ユニークな視点が満載 学生・卒業生グループ展を乞うご期待!
このようなデザインと医療が結びつくことに気付く体験は他にも。白黒写真をフォトショップ(画像編集・デザインソフト)でカラーに色づけしたものを、認知症の方に見てもらい、記憶を刺激する回想療法的な取り組みも行いました。
最近研究室で行った実験では、写真を素材とし、手を動かして触り色づけする表現活動をすると、次にその写真を見ただけの場合でも脳内の触覚野に触覚刺激を再生することがわかっているそうです。そうした研究成果を医療分野にも展開しているといいます。また今、3年生は4人いて、それぞれが卒業制作のためにコスメのパッケージデザインやフィルムカメラを用いた映像制作、ジェンダーをテーマにした広告制作など、それぞれ
が自由に制作を行っています。平尾さんたちの作品が完成するのはまだ先ですが、毎年、2月頃にガレリア新蔵でゼミの学生・卒業生グループ展が開催されているので、ぜひご覧ください。




3年生のうちから毎月1回、卒論をテーマに発表があり、卒業制作に関しても早いスピードで進行中。「佐原先生の引き出しが多いので、ちょっと相談したら、いろんな角度からポンポンと答えが返ってきて、それをもとにまた自分で考えて・・・を繰り返しながら進めています」。ひとつに固執せず、多様な実践の中で得られた知識をパフォーマンスできるような学びです。人形浄瑠璃で入学案内の映像制作を行うなど、多彩なきっかけ
があるのが、佐原ゼミの魅力。
佐原先生のゼミはユニークで、毎週突発的に「これしよう!」と提案があるのだとか。最近ではフィルムカメラで撮影し、自分たちで現像するという作業を体験。
Adobe Reader
閲覧履歴
このページと関連性の高いページ